今日は相続時精算課税を使った相続税の節税について、税理士事務所の新人職員「税太くん」がベテラン税理士である「申之介税理士」に質問する会話形式で解説します。
登場人物紹介
- 税太くん: 税理士事務所に勤める新人職員。税務の現場経験はまだ浅い。
- 申之介税理士: 実務歴20年のベテラン税理士。税太くんの教育係。
相続時精算課税の基本を知ろう

申之介先生、相続税対策のひとつとして「相続時精算課税制度」があると聞いたんですが、正直あまりよく分からないんです。どんな制度なんですか?
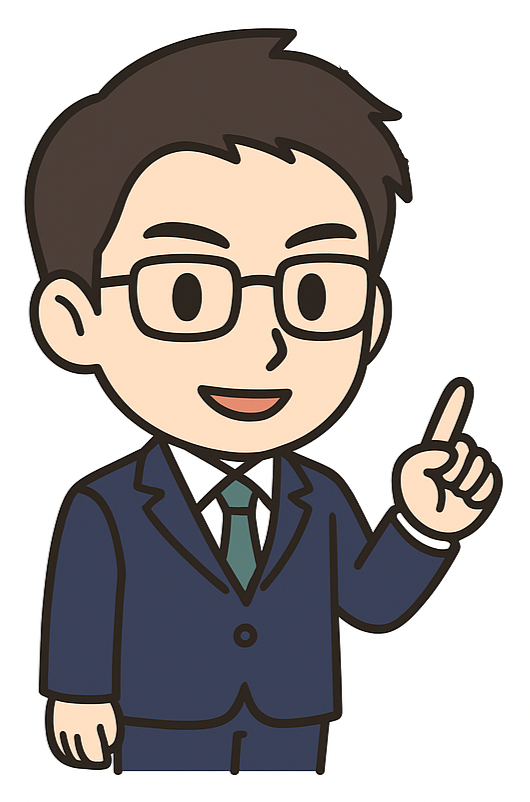
いい質問だね。相続時精算課税は、60歳以上の父母や祖父母が、18歳以上の子や孫に贈与するときに選べる制度で、「一人の贈与者から2,500万円まで非課税で贈与を受けることができる」という制度だよ。それに2,500万円を超えた場合には、超えた金額に対して一律20%の贈与税を払う制度だから、金額によっては累進課税の暦年贈与より贈与税額が低くなることもあるよ。

2,500万円まで非課税なんてすごいですね。でも「精算課税」って言葉がちょっと引っかかります。
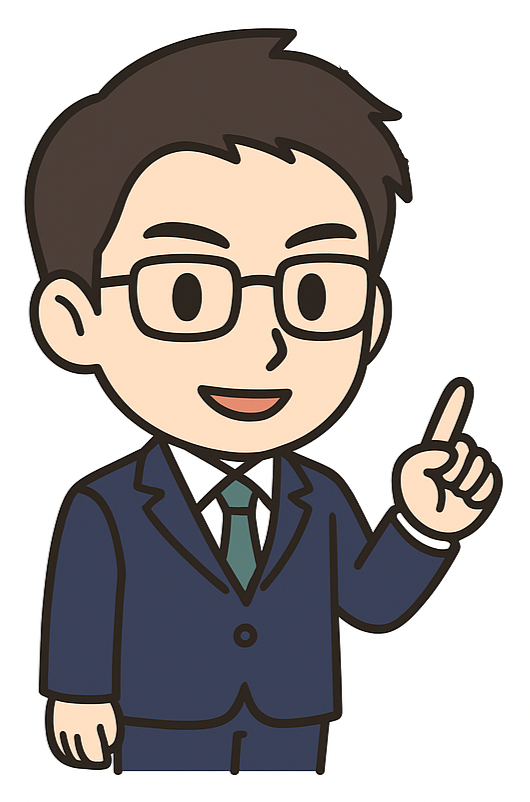
「精算課税」というのは、最終的に相続が発生したときに、それまでの贈与分をすべて相続財産に加算して相続税で精算するからなんだよ。だから、いったんは贈与税がかからなくても、相続時にまとめて精算される仕組みなんだ。
改正で「基礎控除110万円」が新設!

相続時精算課税の場合、暦年贈与みたいに110万円の基礎控除がないと聞いたのですがそうなんですか?
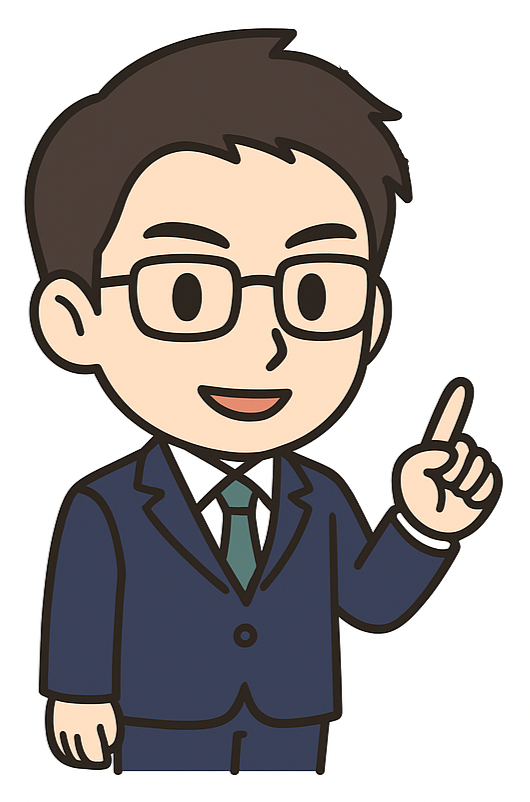
そこが大きく変わったんだ。令和6年1月からの改正で、相続時精算課税を選んでいても「年間110万円の基礎控除が新設され、さらに年間110万円までの贈与であれば、相続財産に加算する必要がなくなったんだ。

えっ!それは大きな改正ですね!暦年課税の場合、相続開始から7年前までの贈与財産は相続財産に加算すると教えてもらいましたが、相続精算課税についてはどうなんですか?
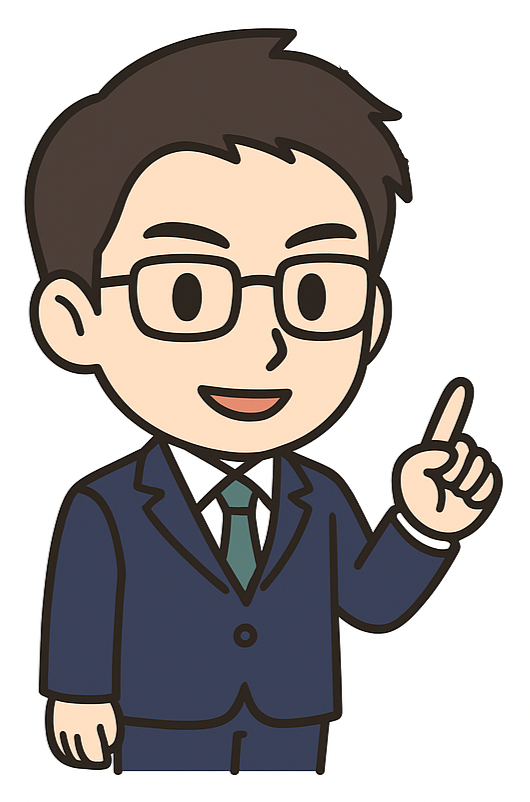
暦年贈与の場合は、相続開始から7年前までの贈与は相続財産に加算する必要があるけど、相続時精算課税については年間110万円以下のものについては加算する加算する必要がないよ。ただし、年間110万円を超えた部分については、何年前であっても相続財産に加算する必要があるからその点は注意が必要だよ。

という事は、年間110万円までの贈与であれば、暦年課税より相続時精算課税の方が、相続税の計算の際にメリットがありそうですね。
値上がり資産を贈与するメリット

その他に、暦年贈与より相続時精算課税を選ぶメリットってありますか?
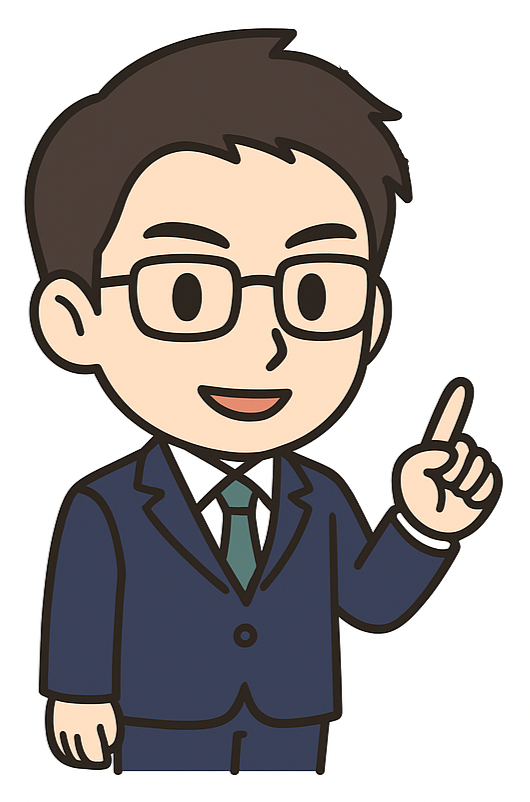
それは「値上がりが見込まれる資産」を贈与する場合だね。
例えば今1,000万円の土地があって、将来相続の時点で2,000万円に値上がりしていたらどうなると思う?

相続のときには2,000万円を基準に相続税を計算されてしまいますね。
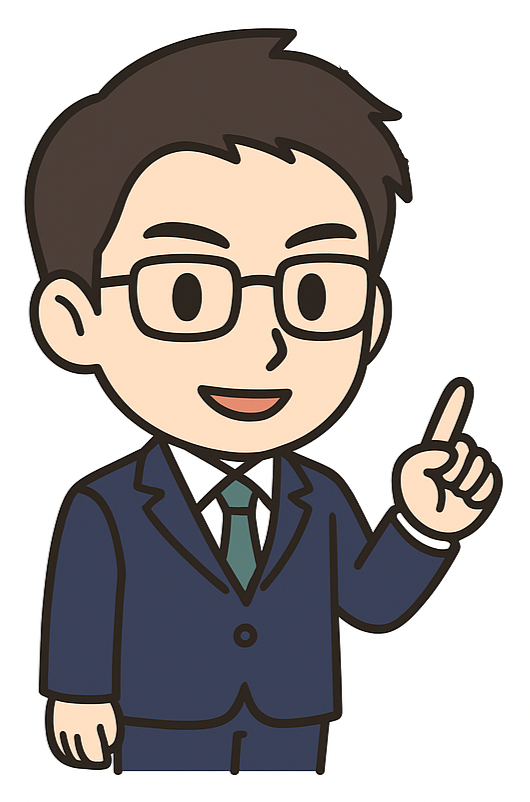
そうなんだ。でも相続時精算課税を使って、1,000万円の時点で贈与しておけば、相続税の計算に加算されるのは「贈与時の価格=1,000万円」なんだ。値上がり分の1,000万円は相続税の対象外になる。

つまり、値上がりが期待できる資産を早めに贈与しておけば、将来の相続税を大きく減らせるんですね!
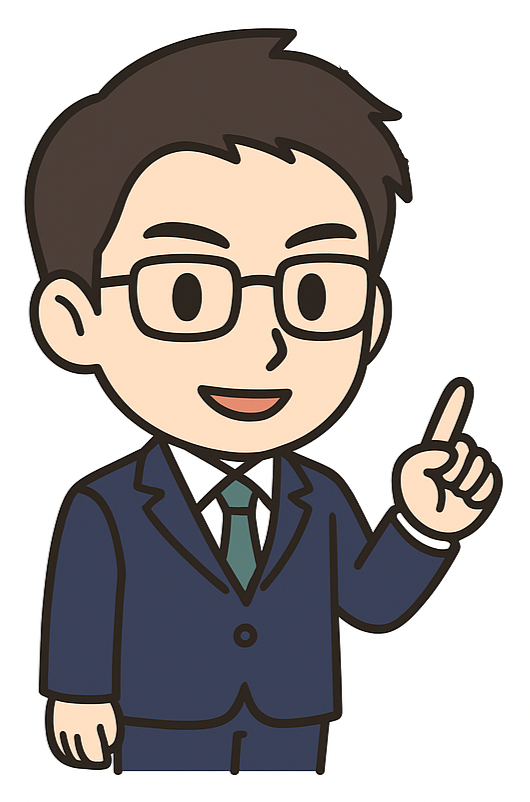
そのとおり!でも、逆に値下がりした場合でも贈与時の価格で相続税を計算することになるから、贈与する財産の選択は注意が必要だね。
その他の注意点

相続時精算課税を選択する際の、その他の注意点はありますか?
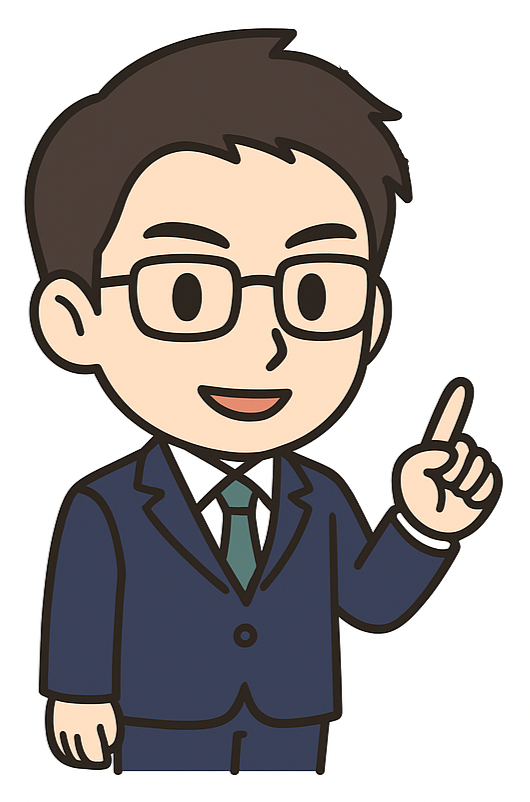
その他の注意点としては、一度、相続時精算課税を選択したら、暦年贈与には戻れないということだよ。だから、選択するときは全体的な資産背景や贈与する財産の種類などに気をつける必要があるよ。
まとめ
- 相続時精算課税は2,500万円までの非課税枠がある
- 贈与した財産は相続税に加算する必要がある
- 令和6年1月以降の贈与については110万円の基礎控除が新設
- 令和6年1月以降の贈与で110万円までは相続税に加算する必要なし
- 相続時精算課税を選択したら暦年贈与には戻れない
参考資料
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務相談には対応しておりません。内容には十分注意しておりますが、正確性・完全性を保証するものではなく、当記事によって生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。税務申告に関しては、必ず税務署や専門家にご相談ください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b2b19e8.345bce68.4b2b19e9.8ecb1c0a/?me_id=1213310&item_id=21206118&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3837%2F9784324113837_1_2.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b5df3ff.e75fc6f7.4b5df400.17f90bb1/?me_id=1285657&item_id=12954745&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F01120%2Fbk479312819x.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)


コメント